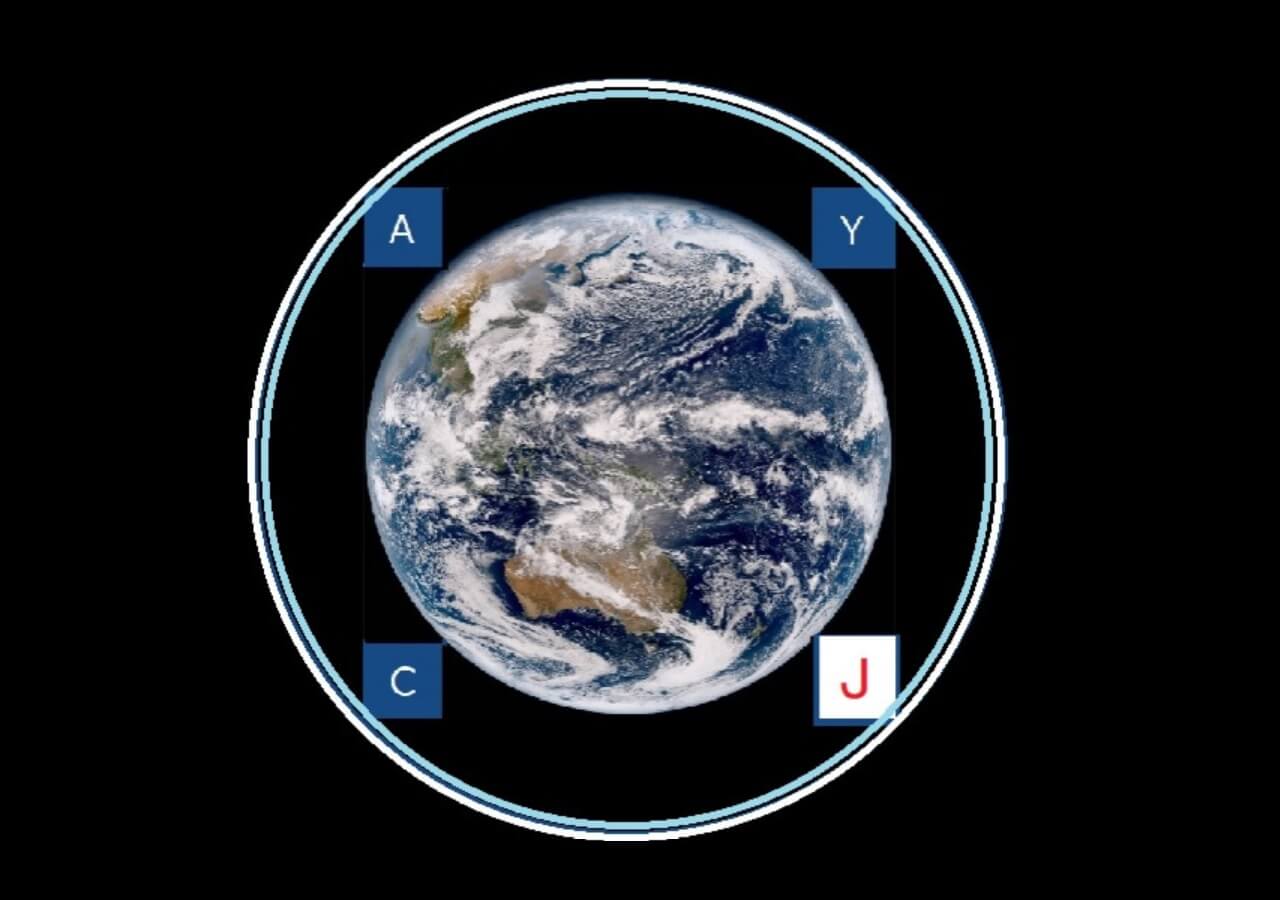1911年(明治44年)1月12日スキーの日
スキー略史(略年表)めも
スキーの歴史については簡単にふれる。
■スキーの始まりはいつ頃?紀元前8000年頃から遅くとも紀元前2500年頃
■スキーの始まりはいつ頃?紀元前8000年頃から遅くとも紀元前2500年頃までにはスキーが始まった。
(※スキーの起源は諸説あり)
紀元前8000年頃中国壁画にスキー
紀元前6000年頃ロシアではのスキーの遺跡
紀元前2500年スカンディナヴィア半島ノルウェースキー狩り壁画
紀元前2500年頃までにはスキーが発祥。
(参考)🔗ウィキペディア-スキー
■スキーの語源:スキー(英語 ski)の語源は古ノルド語「スキース(skíð)」
■スキーの語源:スキー(英語 ski)の語源は古ノルド語「スキース(skíð)」。「スキー(英語 ski)」という単語は、古ノルド語(英語 Old Norse)の「スキース(skíð)」に由来。スキース(skíð)の意味は「割れた木」、「木の棒」、または「スキー」。(引用)The word ski comes from the Old Norse word “skíð” which means “cleft wood”, “stick of wood” or “ski”.[3](出典)🔗英語版wikipedia-History of skiing,Ethmology
古ノルド語「スキース(skíð)」※発音のカタカナ表記スキースは筆者が発音参考サイト(🔗Forvo-How to pronounce skíð in Old Norse※リンク先はノルウェー語版Googleサイト)からヒアリング。耳コピによるもの。場合によりスキーズと濁ると感じる方、たんにスキーとしか聞こえない方もおられるかもしれないがここでは何度か試聴してやはりスキースと聞こえる頻度が多かったのでスキース(skíð)と表記。
古ノルド語 北欧神話
さて、余談だがなぜわざわざスキーの歌の話で古ノルド語(英語 Old Norse)方言のスキース(skíð)とやらまで前提知識としてふれなきゃいかんのか?さっさとスキーソング紹介しろ!と訝しがる方も多いだろう。大分端折るがなぜかというと令和ゲレンデソングとしてインドア派の若者にスキー場に帰ってきてもらいたいときに必須なスキー系アニソンやスキー系ゲーソン(ゲーム音楽など)として重要な北欧神話というトピックを想起していただく上でこのスキーの語源があの『ああ女神さまっ』ベルダンディー(参考リンク🔗ピクシブ)やラグナロクなどの舞台背景につながるからである。
スノーゲレンデのアニメ聖地化
余談ついでにいきおい筆をすべらせてしまおう。このプレイリストの主たるターゲット層はざっくりいえばアラフィフ以上の中高年である。『大人の私も…』と付しているように私スキ世代から90年代スキースノボブーム全盛期世代が令和2020年代以降のスノーゲレンデへの日本人客回帰への一つの方向性だろう。
とはいえ、正直自分もインドア派でスキー場とか面倒といかなくなった輩の一人でもあり若い方にかぎらずおよそわざわざ寒いゲレンデまで行くの億劫という気持ちもものすごくよくわかる。ではそんなインドア派の皆さんもたまにはスノーゲレンデもよいですよと訴求するには何が必要か。それはスノーゲレンデのアニメ聖地化である。
このプレイリストではとりあえず管理人的にはわりと最近見たアニメで印象的だった『五分の一の花嫁』(のスキー合宿シーン)をネタに、かの元メガデスマーティフリードマンがアルペンCM(広瀬香美)カバーなどでスペシャルゲスト参加…的な雪山ゲレンデアニソン妄想mixをぶちこんでいるが。みなさんもご自分のスキープレイリストには好きなアニメや漫画などの推し作品ねたを取り入れてみてはいかが?
スキーはアニメとくにラブコメ系にはほぼ不可欠な冬の定番イベント
もともとスキーはアニメとくにラブコメ系にはほぼ不可欠な冬の定番イベント。
例えば、
1986年3月26日アニメ放送開始『めぞん一刻』高橋留美子
では三鷹さんと五代さんと朱美さんと管理人さんとこずえさんなどがスキー場を舞台にくっつきかけたり嫉妬したり云々の茶番を繰り広げていたことを「まったく…」と若干そしりつつ内心(ぜったい大学生や社会人になったらああいうことしたい)とスピリッツを読んでいた読者も多いだろう。
ああっ女神さまっ藤島康介先生にしろ『めぞん一刻』高橋留美子先生、某トレンディドラマの柴門ふみ先生にしろおそらく70年代漫画雑誌『ぱふ』出身の漫画レジェンド先生方はお忙しくてスキーどころではなかったろう(妄想)。昭和おたく第一世代の方々もあんまりスキー場でさっそうとしているイメージとはつながらない(中略)なにがいいたいかというと別にアニメ・漫画・ゲーム・オカルトなどなどインドア派の方がスキー場とか苦手ということは別に平成にはじまったことではなく昔からスキー場ではしゃぐのが嫌いというのはもちろん当然そういう嗜好もありということ。
杉山卓夫さん(作曲家・編曲家)1987年私スキ1986年めぞん一刻1982年哀しみ2ヤングなど
ちなみに、なぜわざわざわめぞん一刻を引き合いに出すかといえば、
1987年私スキの音楽監督の杉山卓夫さんが実はその前年1986年に『めぞん一刻』関連のサウンドトラックなどを手掛けておられるためである。
したがって私スキの音楽をテーマにする場合めぞん一刻にもふれるのも日本の80年代スキー音楽史には伏線としてつながりがある。
スノーゲレンデはスキーとかスノボしなくても楽しめる
ただ、そんなインドア派の皆さんにもあえてスノーゲレンデを推したくなるのは近年んのスノーゲレンデや周辺レジャーリゾートの多様化・大進化に驚いたため。例えば、ゲレ食(ゲレンデ食事)といえば筆者の個人的イメージではラーメンかカレーの2択でしかもバカ高いという苦い記憶しかなかった。だがしばらく遠ざかっていたうちに平成後期から令和ゲレ食は劇的に進化しているそう。他にも温泉などスキースノボ以外のレジャーも拡充中とのこと。つまり、こういっては身もふたもないが、別にスキーとかスノボやらんでも楽しめそうというのが最近のスノーゲレンデ周りらしい。
そうなると「スキーやスノボはしたくない。でもあのアニメや漫画に出てきたスキー場のゲレ飯や聖地巡りとかはちょっとしたいかも。」というアニメファン。「いややっぱ川端康成『雪国』的な白銀の世界とか一度は体験してみたいし」という文学少女。などなどスキーやスノボが苦手なみなさんにもスノーゲレンデにいってみることは来年の冬シーズンの旅行のアイデアとして温めておかれることはぜひお勧めしたいのである。
軽シンは冬のおたくバイブル漫画
ちなみに管理人的には毎年冬になると碓氷峠(と書いてとうげと読む)軽シン世代なので。(あのマンガ正直第1話以外はしょうもないぐだぐだなのでガンダムおたくとか以外には微妙かもだが)軽シンはむしろおたくマンガとしてのバイブル。そこをはき違えている論評が大杉かも。あのガンプラおたくデフォルメが流行したのはアニメ雑誌界隈ではもちろんOUT(みのり社)やアニメディアや後続のふぁんろーどなど。やミリタリー系プラモの流行はもちろんホビージャパンなどだが。一般青年向け漫画雑誌でそのあにぱろ系の描写を世間一般に広めてくださったのが『軽井沢シンドローム』たがみよしひさ先生の日本のアニメ・マンガ史における重要な功績である。ここで戦前から始まる漫画雑誌のカルチャーと70年代ファントーシュから始まるアニメ系雑誌とが80年代的融合を果たし、のちのさまざまなオタク文化のゆりかごともなっている(とワシは思う)。というわけで、なにが言いたかったかというと筆者は冬のスキーで長野県といえばたしかに私スキの志賀高原や万座スキー場にもそそられるのだがやはりまずは碓氷峠(は冬季運転は危ないので)せめて軽井沢(駅周辺)だけは立ち寄りたい派なのである。たいてい同行者がいると面倒と却下されるのだが。やっぱり個人的期には万座スキー場までいくならその前に軽井沢の「ら・くか」辺りで茶しばいてからのそのそ行きたい。
日本のスキーの始まり 18世紀頃まで露式ストー 1911年近代スキー
■日本のスキーの始まりはいつ?
日本のスキーの始まりは諸説ある。
18世紀頃までに樺太アイヌなどに伝わっていた「ストー」(露式かんじき)
18世紀頃までに樺太アイヌなどに伝わっていた「ストー」(露式かんじき)があったことが間宮林蔵らの報告などに記されている。
1808年(文化5年)間宮林蔵樺太渡航樺太アイヌと遭遇
最近では『ゴールデンカムイ』などの漫画・アニメ作品にも登場。
※作中年1907年(明治40年)2月:日露戦争帰りの杉本がアシリバに出会う。秋田マタギ出身の谷垣らがスキーのような装具(※ストー?)で杉本らを追う。
1907年(明治40)のゴールデンカムイ作品年表でのスキーのような装具についてアイヌ研究家の角田陽一氏によればこれはストー(西洋かんじき)のことではないかとの考察がなされている。筆者はこの記事を拝見するまでストーなど聞いたこともなくまさに慧眼の指摘で目ウロコだった。(参考記事)🔗ゴールデンカムイの謎 12 谷垣のスキーは「フライング」?
ストーとは?
ストーとは16世紀頃から遅くとも18世紀頃までには極東シベリア・樺太などに伝わっていたアザラシの皮などをソールに貼り滑走性を高めた露式西洋かんじき。
スノーシューの一種とされるが、日本においては、縄文時代から始まるかんじき類から、明治後期とされる近代スキー黎明期まで、すなわち江戸時代(16世紀~18世紀頃)の樺太アイヌなど局所的ではあるが、かんじきからスキーへの技術開発移行期に存在した、かんじきとスキーの間をつなぐ重要な民具(民俗学的装具)。
ストーの語源は不明。あくまで筆者の仮説だがおそらくスニガストープエ(ロシア語снегоступы 英語 snowshoe 日本語スノーシュー 西洋かんじき)が訛ったものか。すなわちスニガストープエ(ロシア語снегоступы)語中のストー(сту)の略か。
(以下蛇足ながら)
さて、そんなストーについて気になったので少し調べてみたがあまりネット上でそれ以上の情報が得られなかった。以下、あくまで素人筆者の考察(仮説)だが「ストー」についてネット上の記述が少ないので一応英語版やロシア語版wikipediaで調べたことから、私見を付しておく。なお、私的仮説でwikipediaの要約ではない。
あくまで私見ながら、おそらくこのストーとは、16世紀頃にシベリアのバイカル湖はアルタイとバイカル湖の地域で登場し、16世紀まで広く普及していたスニガストープエ(ロシア語снегоступы)すなわちスノーシュースキーもしくは西洋かんじきのことではないかと考える。
16世紀はスキーの歴史において、スノーシューから滑走スキーへとスキー技術の開発移行期にあたるそうだ。北欧では滑走スキーがすでに使用されてた。
1555年ローマにて出版された『北方民族の歴史』著者のオーラヴ大司教はラップランド人の冬の狩猟技術としてスキーを紹介している。すなわち、近代スキーのルーツとしてはすでに16世紀シベリア極東地域でストー(西洋かんじき)が登場する以前に北欧ラップランド起源のスキー装具がスイスなどのアルプス北側エリアからアルプス東南エリアのイタリア(ローマなど)まで西欧圏に伝わっていたことがうかがえるため、ストーが(近代)スキーのルーツという言い方は直接的には言い難い。形状的にもストーはスノーシューの一種という見方が英語版ロシア語版wikipediaの説明がされている。もちろん同じ雪山を滑降する機能的に言えばストーはスキーのルーツのひとつという説明はあるだろう。ただ、史実的にはアザラシの皮という樺太や北海道(道北・道東エリア)でのみ採集される原材料の制約もあり、極めて優れたシベリア狩猟民族や樺太アイヌの伝統技術による民具ではあるが、本州以南の日本では実際に普及はしづらかった側面もあろう。そのためスキー連盟による公式の日本のスキー発祥は1911年(明治44年)1月12日(スキーの日)とする現在の公式見解を否定するものではない。ただ、筆者の私見ながらむしろストーは90年代頃から一部で流行したミニスキーの原型というルーツ性は指摘できるかと思う。ミニスキーは操作性が難しい上級者向けの高度なスキーだが、おそらくストーを巧みに操っておられた樺太アイヌの技能は類まれなことだったろう。加えて、そんな難しいストーを操りながら、狩猟など別の技能も駆使していたことは、例えれば雪上での流鏑馬とも付言したくなる極めて高度で優れたアイヌの伝統技能であり、その文化財(有形・無形)的価値は高いと思料する。
ストーとは16世紀頃から遅くとも18世紀頃までには極東シベリア・樺太などに伝わっていたアザラシの皮などをソールに貼り滑走性を高めた露式西洋かんじき。
スノーシューの一種とされるが、日本においては、縄文時代から始まるかんじき類から、明治後期とされる近代スキー黎明期まで、すなわち江戸時代(16世紀~18世紀頃)の樺太アイヌなど局所的ではあるが、かんじきからスキーへの技術開発移行期に存在した、かんじきとスキーの間をつなぐ重要な民具(民俗学的装具)。
ストー関連語句?
・スニガストープエ(ロシア語 снегоступы)英語 snowshoe
・ストプニー(ロシア語 ступни)英語 feet
・リュージュ(ロシア語 Лыжи)英語 ski
1900年代(明治40年代)頃 日本の近代スキー黎明期
1908年(明治41年)
1911年(明治44年)1月12日 スキーの日
公的には、1911年(明治44年)1月12日スキーの日とされているように新潟県で体系的な近代スキー技術の講習がおこなわれたことが日本の近代スキーの始まりとされる。
1911年(明治44年)1月12日スキーの日