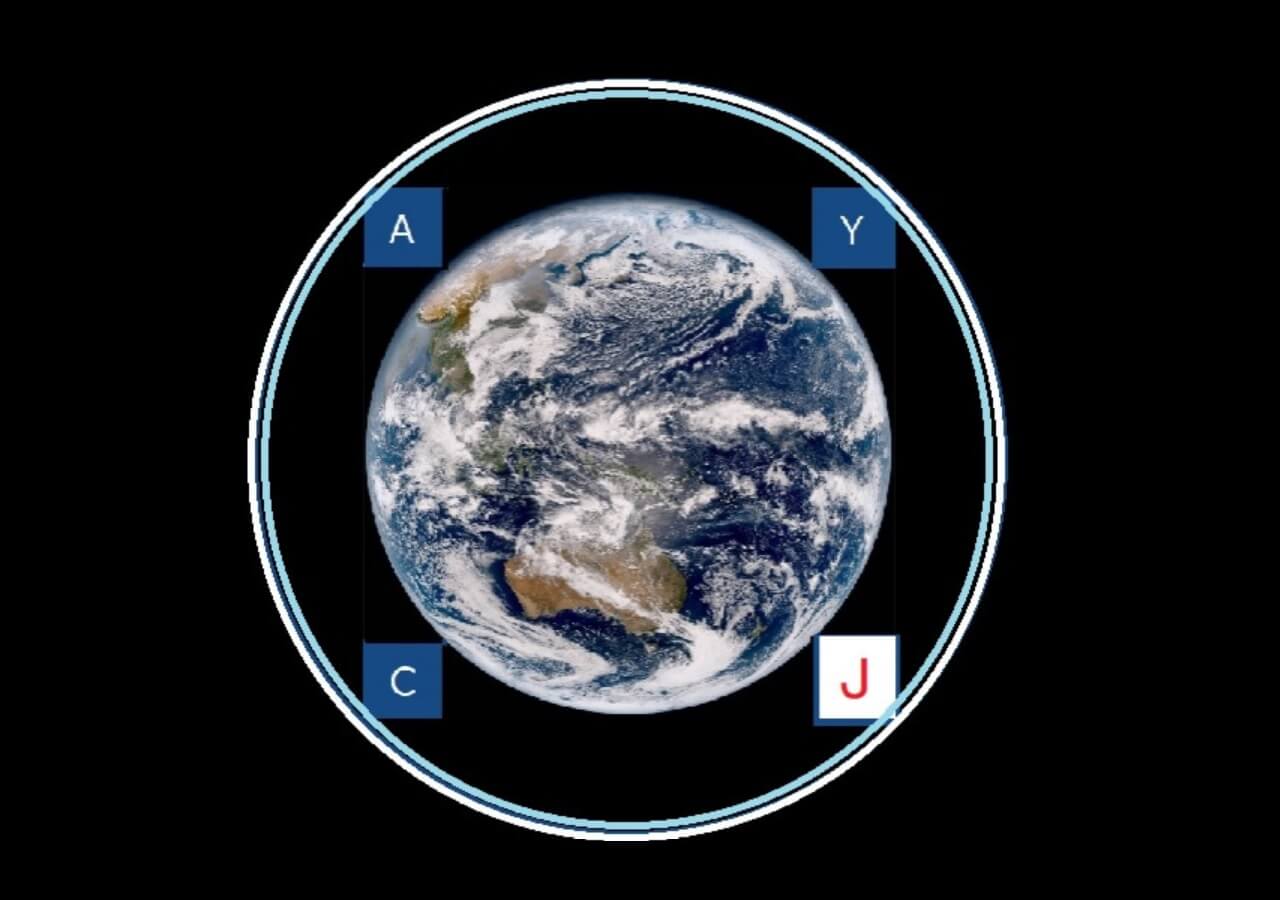年代の英語はdecadeも含まれる。というより年代の英訳としては上位の候補だろう。一般的な日本語でも年代の使用頻度からいえば2020年代、2010年代、2000年代…という具合に「〇〇年代」という用例が主かと思われる。
たしかに「年代(英語 decade)」にはまず「十年(英語 decade)」という意味もある。また「年齢(英語 age)」や「期間(英語 period)」「時代(英語 era)」という意味と重なる部分もある。国語辞典(日本語の辞書)でも「年代」の語義には、年月、期間、年数、年齢層、などが含まれるとされる。
ただ、日本語の日常的な言い回しからすればやはり「〇〇年代」といった言い方のほうが圧倒的に頻度が高いだろう。筆者個人の体感では9割以上「〇〇年代」(英語 decade)という使い方。年代別にしても90年代80年代70年代というように西暦の十年代(英語 decade)が比較的多い。たしかに年代別には年齢別という意味と重なるが年齢の年代別をいう場合は世代別ということが多い気がする。いずれにせよ、年代の意味では日本語では「〇〇年代」という用例の使用頻度が多いと思う。
さて、わざわざ書くほどのこともない英語の基本単語だと思っていたがどうやら英語翻訳では意外と悩ましい言葉のようだ。
英語では「〇〇年代」という場合”〇〇s”もしくは”the〇〇s”。すなわち「年代(decade)」に相当する英単語は含まれない。
例えば「2000年代」の英語は”2000s”もしくは”the 2000s”。英語圏でも数字表記が一般的だがもし文字で書くなら”two-thousands”または”the two-thousands”。発音もこれらの文字の発音(カタカナ発音「トゥーサウザンズ(略記ツーサウザンズ)」または「ザ・トゥーサウザンズ(略記ザ・ツーサウザンズ)」ネイティブ発音カタカナ「トゥーサウザン」語尾のsは消音化してほぼ聞こえない。他に、英語版wikipediaなどでは、the’00s、the aughts、the noughties、という言い方もあるようだ。The 2000s (pronounced “two-thousands”; shortened to “the ’00s” and also known as “the aughts” or “the noughties”) 🔗source:en.wikipedia-2000s🔗(筆者注)nought意味zero(0)。aught意味anything at all。いずれにせよ、ふつうは英語で2000年代といえば2000sが一般的だろう。
問題はここで和英翻訳のズレが生じること。
「年代」に関する日本語と英語の翻訳の問題点としては、日本語「〇〇年代」と英語”〇〇s”の「年代」と”s”の対応関係が悩ましい(わかりづらい)点。日本語では書くときは確かに英語にならって90s80s70sなどの略記もある。ただ話すときに「ナインティーズ」とかエイティーズとかセブンティーンズとかいわない。(きっと英語かぶれのきどった輩と思われるから絶対に嫌だ。)日本人なら〇〇年代と年代をつけるのが普通。一方、英語では”90s”を”90s decade”ということはあまりないようだ。”90s”や”the 90s”または”1990s”や”the 1990s”。ビジネス英語などでもせいぜい”the”をつける程度でていねいな英文のニュアンスはでる。
そういやそうか、という程度の話かもしれない。ただ「年代」の英語翻訳で”decade”が候補にあがってこないのは、こうしたそもそもの日本語と英語の「〇〇年代(英語”the〇〇s”)」の言語表現の違いが要因かもしれない。
ずっと不思議に思っていたが、Googleでも「〇〇年代」と「〇〇年」を取り違えるケースが多いように感じていた。
2025年2月18日時点で英語版GoogleのGoogle translateで「年代」を翻訳しても「decade」という訳語の候補が見当たらなかった。
(修正前)「年代」(Google翻訳)「year」(age, period, date, era)
一応「年代」のGoogle翻訳修正案として「decade」も加えてもらうように提案はしてみた。
(修正後)「年代」(Google翻訳修正案)「decade」(age, period, era)
いずれにせよ、「年代」の英語は、はじめは正直Google翻訳の誤訳なのかとも思ったが(失礼!)、どうやら意外と日本語と英語の言語表現の違いという根本的な話のようだ。
とはいえ、普段の作業などではやはり年代を年ととりちがえる英語の誤訳は困る。よく使うGoogle翻訳さんには修正案も提案しておいたので、できればいずれ修正されることを期待したい。(※個人の感想)